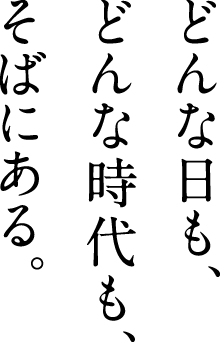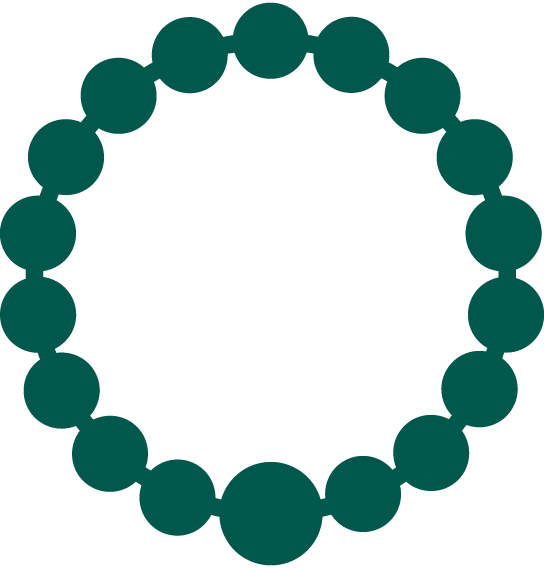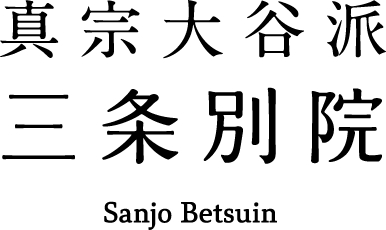三条別院に想う
MEMORIES OF THE BETSUIN
2023年2月1日
酒場カンテツから三条別院に想う
関本 秀次郎 氏(酒場カンテツマスター)
▲今回は9月の彼岸会で精進カレーをお願いした、酒場カンテツのマスターに執筆していただきました。関本氏はYOUTUBEチャンネル「燕三条TV」等、多方面で活躍されていて、三条別院への想いをお聞きしました。
生まれも育ちも本寺小路だったもので
歩いて通えるから松葉幼稚園に
通っていましたし
遊び場はとなると、大抵、
別院だった記憶があります。
かくれんぼ、たか鬼、缶蹴りと、
昭和な遊びをしたものです。
少し大きくなると、御坊様の夜店でデートしたり、ツッパリな人にカツアゲされそうになった思い出も、あったりする。
そんな自分が、最近、三条別院さんへ仕出しをする機会が増えてきている。
精進弁当を作った事がキッカケで
古典な精進からスパイスカレーなど様々な精進料理をお届けしてきました。

板前修業時代も、ガチガチの精進料理は
作っていなかったので
一から勉強しながらの、
楽しい仕事になっています。
子供の頃から勉強が嫌いで、歴史なんて、
勿の論、教科書も開かなかったが
オッサンになるにつれて
「昔は今より新しい」と、気づき、
事あるごとに、昔を調べるようになり
親鸞聖人も、ちょっとネットで調べてみると
なかなか波乱万丈でアナーキーな人生だなーなんて思った時もあったり。
昔の料理を調べると
「煎り酒」なる、昔ながらの調味料だったり
「すり流し豆腐」の様に、
当時人気の有った料理や
「麩の焼き」なるデザートなど、、、、
調べれば調べるほどワクワクする料理がでてきて
自分で作り、食べ、
当時を思い描いて楽しんでいます。


個人的な考えですが
料理も文化も政治や争いごとなど
歴史を振り返ると、案外答えが出やすいのでは?と思う今日この頃です。
「昔は今より新しい」を胸に
この街のこと、料理のこと、
自身の商売のことなどを
昔を紐解き、楽しく生きていきたいものです。

関本 秀次郎 氏
(酒場カンテツ店主)
次回の「三条別院に想う」は、
小俣 福子 氏(第17組 妙音寺門徒)
よりご執筆いただきます
▲次号は新しく別院教化審議会委員に就任していただいた小俣氏に依頼しました。
2022年10月5日
慶讃法要三条教区お待ち受け大会に際して
山﨑 超 氏(第11組 淨福寺)
▲今回は5月の慶讃法要お待ち受け大会で司会をされた山﨑超さんにお話をお聞きします。
2022年5月29日、三条別院にて三条教区宗祖親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要お待ち受け大会が勤修されました。
初めは先輩から、お待ち受け大会の司会のお役目を指名してもらえた時には、お待ち受け大会がどんな雰囲気で開催されてるのかをよく知らなかったので特に何も考えもせず引き受けました。
そしてお待ち受け大会本番に近づくにつれ打ち合わせ会議などで出席される方々はこれまで三条別院に深く携わってきたベテランの方々ばかりで、これは絶対に失敗出来ない、と楽観的だった気持ちが一気に不安に変わりました。
お待ち受け大会前夜は新門様の歓迎会が開催されました。当日の予行練習も兼ねて歓迎会の司会もさせていただきました。職員さんに原稿を用意してもらい万全の準備をしてもらいましたが、結果は散々でした。原稿の言葉は間違えるし、言葉もスムーズに話せない。「ほんとにこの男が総合司会で大丈夫か??」と会場中に心配の雰囲気が漂い黄信号がともりました。歓迎会終了後はホテルに戻り、このままだと明日のお待ち受け大会を自分のせいで大変な事にしてしまうと危惧してホテルの部屋で総合司会の当日原稿を何度も読み返し練習しました。
そして、お待ち受け大会当日を迎えます。天気は快晴。気温も高かったです。
最初はお待ち受け大会記念植樹式が開催されました。とても暑い中でしたが植樹式担当の方々を中心に無事に植樹式を終えることができました。
そして本堂に戻りいよいよお待ち受け大会本番が始まります。
各地方から300人以上の人が集まり、本堂内は聞法を求めている方々の熱気に包まれて私はこれまでに感じたことがない緊張とプレッシャーを感じました。
自分自身も想いに応えなくてはならないと自分を奮い立たせて、そこから何とか当日の司会を無事に失敗なく終えました。
改めて総合司会を経験して感じることは、三条別院の法要はたくさんの方々の思いの結晶であり、一つのお待ち受け大会の中で沢山の方々がお待ち受け大会を成功させたいと結束していることに自分は感激しました。本当にいい経験でした。
余談ですが、自分はお待ち受け大会の翌日に東本願寺に用事があり本山の境内を歩いていると、たまたま新門様と本山でお会いする機会がありました。
「昨日の三条別院のお待ち受け大会は本当に素晴らしかったです」とお褒めの言葉をかけて頂きました。
山﨑 超 氏(第11組 淨福寺)
○次回の「三条別院に想う」は、
関本 秀次郎 氏
よりご執筆いただきます
▲次回は9月の彼岸会で精進カレーをお願いした、酒場カンテツのマスターです。YOUTUBEチャンネル「燕三条TV」等、多方面で活躍されています。三条に対する想いと、三条別院への想いを、執筆していただきます。
2022年9月18日
三条別院有志の会庭講の「好」を考える
風間 正喜 氏(第19組満願寺門徒 庭講代表)
▲三条別院の庭講の代表を務められていた大泉三郎氏が6月30日にお亡くなりになりました。今回は後任として代表を引き受けていただいた風間正喜氏より執筆いただきました。
【三条別院有志の会庭講の「好」を考える】
三条教区19組の役員で同朋会館に行っていたころ、三条別院列座斎木さんより三条別院をきれいにしたいので、掃除の手伝いをしていただけませんか、との話でしたので、「草取りでもすればいいのか?手伝えるな」と、引き受けました。実際はただの草取りではなく、参道の側溝のふたをはがし、溜まった土、かれた葉っぱなど取り除き作業。ただの草取りとは違い、めぇいっぱぇい汗をかかされました。午後から13日の法話、気持ち良く聞くことが出来た記憶があります。今振り返ると、別院の阿弥陀様がさせたのかな、と思います。この後受けた法話は睡魔をこらえて聞くことが多く、内容は跳んでいます。これがまた、我に返った時の「悪い・しまったー」の入り混じった気持ちよさ。たまりません。阿弥陀様にも勘弁してもらえると思います。書院から見る庭を、「浄土庭園」にしたいと思っておりますので、三条別院の阿弥陀様が「まだだ、まだだ」と、呼びつけているように思えるうちは、続けたいと思います。令和4年6月30日、三条別院有志の会庭講代表の大泉三郎氏環浄の知らせを受け、突然の事、戸惑い、受け入れがたい気持ち。手を合わせ浄土庭園へお念仏申します。小生が後を引き継ぎます。
【仏壇の前に座り阿弥陀様に合掌して初心忘れず】
お内仏の前に座り左右の手を合わせ、初心忘れず回想してみました。赤本を開き、三帰依文、正信偈、念仏和讃、回向、声を出して読み上げて、仏壇の阿弥陀如来と向き合い今日も良かったかなと、ちょっとだけ一人反省会。ですが、どうしてもわからないことがありすぎるんですね。何せ800年前の書き物と格闘して声を出して読み上げても、世の中の元号は令和4年ですから。とはいえ、『真宗の生活』(教化冊子2022年版)「篤く三宝を敬え」によれば、聖徳太子(昨年が1400回忌)『十七条憲法』第二条は「其れ三宝に帰(よ)りまつらずは、何をもってか枉(まが)れるを直さん」と結ばれます。三宝に帰依しなければ、現代生活の中のさまざまな枉ったことが直されないというのです。三帰依文の仏・法・僧の事が書かれています。凡夫にもわかります。うんうんうん。
正信偈はたくさん解釈資料が出ています。同朋新聞2019年11月号より2022年7月号まで33回連載がありました。(井上尚実大谷大学教授著)新聞を見ていて何故か嘆佛偈をやらされました。宗祖親鸞聖人御誕生850年立教開宗800年慶讃法要に併せて『親鸞聖人の直筆にふれる正信念佛偈』を私は購入しました。すごくいい本です。語註(1から88まで)も解りやすく現代語訳です。次に回向。
願以此功徳 平等施一切
同發菩提心 往生安樂国
「願以此功徳」(和訳歌詞)
願わくは一切世界の人々と この出会いの喜びをみな平等に分かち合い ともに仏になる心発して 阿弥陀みほとけの安楽国に生れ 生きてはたらく身とならん
音楽法要の楽譜の和訳歌詞が出来て分かりやすくなりましたね。
問題は800年前に作られた念仏和讃。どなたかわかるようにしていただけないでしょうか、お願いします。
風間 正喜 氏(第19組 満願寺門徒、庭講代表)
○次回の「三条別院に想う」は、
山﨑 超 氏(第11組 淨福寺)
よりご執筆いただきます
▲次回は5月の慶讃法要お待ち受け大会で司会をされた山﨑さんにお話をお聞きします。
2022年8月22日
慶讃法要三条教区お待ち受け大会に際して
石塚 亜里 氏(第15組長泉寺坊守)
▲5月29日に宗祖親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要三条教区お待ち受け大会が開催され、2023年の本山における本法要に向けての準備も始まってまいりました。今回は慶讃法要実行委員であり、教区坊守会副会長でもある石塚亜里さんに執筆をお願いしました。
私が三条別院に初めてお参りしたのは21年前、結婚後すぐの報恩講でした。「お取り越し荒れ」と呼ばれるあられが降る中、お念珠ひとつ持ってのお参りでした。
鮮やかな仏旗がはためく本堂を見上げ、外にまで響く読経の声に圧倒されつつ、いざ一歩入ると、そこは別世界でした。
まだ紋付羽織姿のお参りの方々がおられた頃です。在家から嫁いだ私にとって、見るのも聞くのも、何もかもが初めてのことでした。
ピカピカに磨き上げられた仏具の前で、雅楽と共に入堂してきた、色とりどりの法衣を着たお坊さんたちの熱気あふれるお勤めは、ただただ圧巻でした。
遠くでお勤めをする夫の背中を見つけた時には、感動や安堵や興奮が入り混じり、何か祈りにも似たような気持ちで泣いたことを覚えています。
2022年5月29日、三条別院にて三条教区宗祖親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要お待ち受け大会が勤修されました。
この度のお待ち受け大会では、私たち坊守会は報恩講と同様に新門様並びに御来賓のご接待と帰敬式受式者とスタッフのお昼のお給仕を担当させていただきました。
ご接待は多岐に渡ります。
まず掃除。部屋の中、廊下だけではなく外の草むしりを率先してくださった坊守さんがおられました。窓が得意だと言い、透き通るほど磨いてくださった坊守さんがおられました。
次に茶器の準備。柄が季節に合わないので、ご自坊から銘々皿をお貸しくださった坊守さんがおられました。使い捨てのおしぼりやおしぼり置き、懐紙をお持ち下さった坊守さんもおられました。
お茶菓子の手配。別院周辺の和菓子屋さんを探し、また、軽くつまめるもので、且つ新潟らしさがあるものを探して奔走してくださった坊守さんがおられました。
この度は50年に一度の慶讃法要お待ち受け大会ということで、多くの坊守さんが色紋付の着物で当日に臨みました。
あの暑い日に、新門様に冷やしたお抹茶を飲んでいただきたいと、氷を準備してもらい急いでお抹茶を立て、後堂まで走った坊守さんもおられました。
その抹茶茶碗も、もし足りなければとお持ちくださった坊守さんがおられました。見つけたゴミをそっとたもとに隠し、履物を揃える坊守さんも。
かっぽう着姿で楚々と立ち働く坊守さんは、なんと素敵だったことでしょう。
ご門徒さんやスタッフさんへ笑顔を絶やさず、くるくるとお給仕をこなす坊守さん達がおられました。
当日来られないからと、念入りにお掃除や仏具のお磨きをされた坊守さんもおられました。
私たちは、お預かりするお寺での、各々の日々の動きを精いっぱい発揮させて頂きました。貴いご縁を頂戴し、ありがとうございました。
坊守会役員の任期はあと1年。この秋の報恩講が、任期中としても、また三条教区としても最後のお勤めになります。多くの皆さんと力を合わせてお勤めしたいと思います。
石塚 亜里 氏(第15組長泉寺坊守)
○次回の「三条別院に想う」は、
風間 正喜 氏
(第19組 満願寺門徒、庭講代表)
よりご執筆いただきます
▲三条別院の庭講の代表を務められ、また報恩講実行委員参拝部の委員もお願いしていた大泉三郎氏が6月30日にお亡くなりになりました。次回は大泉さんの後任として庭講代表を引き受けていただいた風間正喜氏より執筆いただきます。
2022年7月21日
慶讃法要三条教区お待ち受け大会に際して
大溪 文祥 氏(第24組榮行寺住職)
▲5月29日に宗祖親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要三条教区お待ち受け大会が開催され、2023年の本山における本法要に向けての準備も始まってまいりました。今回は慶讃法要実行委員であり、報恩講実行委員でもある大溪文祥さんに執筆をお願いしました。
2022年5月29日、宗祖親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要三条教区お待ち受け大会が三条別院にて厳修されました。今回のお待ち受け大会ではスタッフとして参加させていただき、当日は帰敬式を担当させていただきました。お待ち受け大会では39名のご門徒が受式されましたが、受式前の緊張した表情と受式後の写真撮影での笑顔がとても印象に残る帰敬式となりました。
お待ち受け大会でもスタッフとして参加させていただきましたが、毎年執り行われている三条別院お取り越し報恩講では、教化部会の一員として参加しています。
お取り越し報恩講をお迎えするにあたり、教化部会は法話講師の選定、ポスター・パンフレットの作成、シアターサンジョーゴボーの演目決めなどを受け持っていますが、お取り越し報恩講の当日に私が担当するのは本堂内での司会進行です。参拝者にその日の日程をお知らせするのはもちろんのこと、参拝者から法要について質問を受けるなど多くのご門徒さんから話しかけられる立場でもあります。
2020年のお取り越し報恩講は日本中があらゆる行事を中止するなか、殆ど内勤めと言っていいほど参拝者が限られたなかで勤まったことが今でも思い出されます。毎年賑わうお土産売り場もなく、お斎もお弁当で人との間隔を開けて黙食で済ませるなど、多くの参拝者をお迎えして勤まるのが当たり前のことと思っていた私にはとても寂しく感じました。翌年には、一部制限があったものの団体参拝やお土産売り場などが再開され、少しずつではあるが活気が戻ってきました。
新型コロナウイルス感染症の影響もあり、家にいながらパソコンなどの画面を通じて会議に参加できたり、今回のお待ち受け大会や昨年のお取り越し報恩講でもそうであるが、直接足を運ぶことができなくてもリアルタイムで配信される動画を視聴することで参加できるようになりましたが、直接足を運ぶことで私自身がとても大切な時間を戴いていたことにあらためて気付かされたように思えます。
お取り越し報恩講は一年間のうちのたった4日間でしかないですが、その期間中に教化部会の仲間だけでなく、先輩や後輩、参拝されているご門徒さんと話をする時間を戴いていたことに感謝しつつ、今年もお取り越し報恩講の準備に取り掛かろうと思います。
大溪 文祥 氏(第二十四組榮行寺住職)
▲本年度のお取り越し報恩講について
なお、本年2022年11月5日(土)から8日(火)のお取り越し報恩講の講師及び基本日程が決定しております。11月5日のお待ち受け音楽法要・初逮夜から8日結願日中まで全10座の法要は例年とほぼ同日程となっており、6日から8日までは本山鍵役が御参修予定です。
法話講師は5日、6日は青木 玲 氏(九州大谷短期大学准教授)、7日、8日は廣陵 兼純 氏(能登教区満覚寺、節談説教)です。昨年より団体参拝の受入れも再開しましたので、ぜひ各組でご計画いただければ幸いです。なお、本年は第17組、第18組、第20組、第22組を職員巡回させていただく予定です。
○次回の「三条別院に想う」は、
石塚 亜里 氏(第15組 長泉寺坊守)
よりご執筆いただきます
▲次回は教区坊守会副会長で慶讃法要実行委員の石塚氏より執筆いただきます。