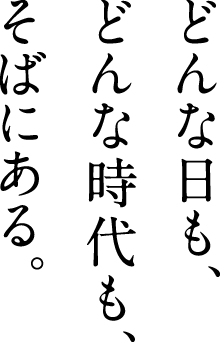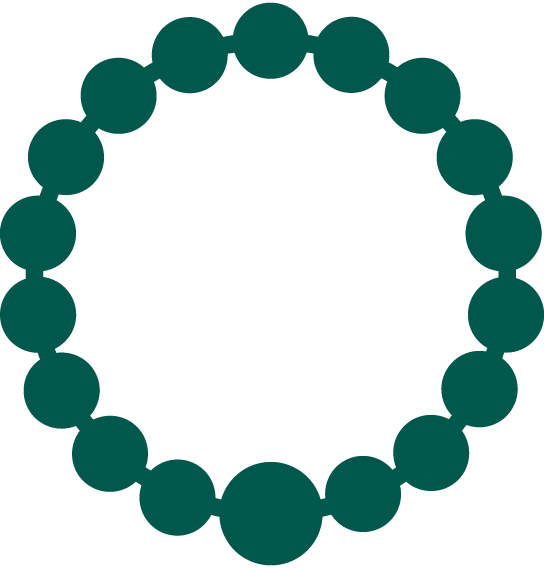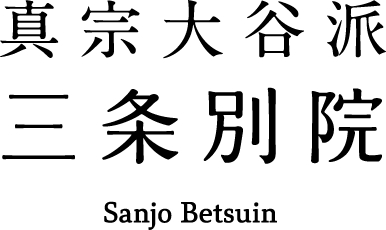ブログ
BLOG
2022年10月1日
教区坊守研修会 開催報告
開催日 2022年9月16日(金)
講 師 梅澤 未有 氏 (高田教区第1組光照寺)
テーマ 「私の話 死にたいと言われたら」
報 告 藤岡 慶子(佐渡組 淨願寺・教区坊守会役員)
最初に、梅澤先生の生い立ちのお話から始まりました。梅澤先生のお母さんは、「死にたい、死にたい」と話す躁うつ病の患者さんでした。今から四、五十年前は精神科しかなくて、今のような進んだ医療は受けられなかったそうです。そのため梅澤先生と妹さんは、お母さんから虐待を受けていたそうです。毎朝トラブルがあり、学校へも遅刻寸前に通ったそうです。聞いていても、胸が痛くなるようなお話でした。梅澤先生が成人してから、お母さんは自殺してしまい、立派な遺言が残されたそうです。お母さんとのこのような関係がある中で、現在お寺でたとえば、自殺した人のご家族に、ただ、「たいへんでしたね。」というだけでは、いやだという思いがあるそうです。
講師の梅澤未有先生
次に、厚生労働省の日本自殺統計をもとに話されました。バブル崩壊頃には、三万人になり高止まり、2006年自殺対策防止基本法ができ、2016年頃から下がり、2012年には二万人に下がった。自殺予防週間もでき、令和二年になると、男性の自殺率が下がった。女性がやや上がっているのが見落とせない。自殺の原因は、イジメ、パワハラ、その他。死にたいとは、死にたいくらいつらいということで、本当はいきたい。
死にたいと悩みを相談されたら、
①評価せず話を聞く
②全部受け入れる
③無理ないよねとよりそう
④近くに助けてくれる人がいるかどうか聞く
ことが大切。
講義の様子
自殺遺族に寄り添う仏教が求められている。「苦」をケアすることが大切。グリーフケアのワークショップがある。
座談後のまとめの講義では、自分が遺族のケアをすることによって、梅澤先生自身もケアをうけたいと学んでいった。親鸞聖人は、浄土にいけると言っている。仏教では、自殺はいけないと言っていない。自殺は社会の問題。
自殺を苦しんでいる人、遺族の方の苦しみも身近に多くある。お寺のケアを学んでいくことの大切さを思いました。
坊守登録はしておりますでしょうか? 詳細はこちら ➡ 坊守籍簿登録について
2022年10月1日
長岡地区・新潟地区合同女性研修会 開催報告
開催日 2022年9月5日(月)
テーマ 『観経に聞く 私の現場』
講 師 細川 好円氏(第17組護念寺住職)
報 告 古俣 福子 (第17組妙音寺 女性研修会スタッフ)
細川先生初めての講義を受けて、とても率直で解り易く、私達の生活と深く関わっているテーマだと思いました。
今がずっと続いていくと信じて、大切な事を後回しにして生きている私達は、何が大切であるかも判っておらずに生活を送っています。
講師の細川好円先生
日々、全ての事が移り変わって、様々な考えが浮かんでは消えていき、それに惑わされて思い悩んでいます。今日の一日は、最初の日であり最後の日なんだという自覚も無いまま、何気なく過ごしてしまっている。そして何処か別のところに行けると思って生きてしまっている。しかし、その場から一歩も動いていない事実を見ていない。今いる所以外に自分の人生は無いのだという覚悟を持って、「本当の人間になりたい」と願わなければ何をやっても上手くいかない。
お釈迦様が指し示してくれた 南無阿弥陀仏 は、「本物の人間になりたい」と願えば十八願は叶うのだという真理なのだ。全ては、今自分が立っているところ、そこが現場なんだと自覚して、一生懸命生きていくのだ。
と、力強く教えていただき、何が大切なのかを見返す事ができました。
各班別座談の様子
座談会でも、各班で活発な意見が出たようです。まとめの講義では、先生の「私に隠す事は何もない。」とご自身のお話などをしていただいて、笑いが会場内に溢れていました。
2022年9月7日
『お寺で帰敬式スタートアップガイド』鋭意作成中!!
2022年7月25日
第15組称名寺「お経に親しむ会」同朋の会にお邪魔しました。
称名寺(見附市)では10年前から「お経に親しむ会」が開催されてきましたが、この度同朋の会として登録をされました。
お経に親しむ会は月二回、お勤めと住職による「正信偈」のお話し、質問やお茶飲み話しが主な内容です。
この日もご門徒の佐々木さんが導師として、真宗宗歌、正信偈(同朋奉讃)のお勤め、皆さんで声を合わせて御文を拝読し恩徳讃斉唱。
ご法話の後、この日は年に二回の食事会の日で、納涼会としてお弁当をいただきながら楽しく歓談させてもらいました。
ご門徒の佐々木さん・大久保さんからお話しを伺いました。
昔、お寺の手伝いをしてもらっていた芳賀さんから「称名寺にはお経会がないから作ったらどうか」と進められて、仲間3人で立ち上げたのが会の最初でした。住職の居ない大変な時期もあったけどここに集まっている仲間が中心となって協力しながら乗り越えてきました。
今では菊井住職と一緒に、お経会や年に二回お盆と除夜の鐘の時の「竹灯籠」など、お寺にとっても町にとってもいい活動が出来てると思っています。
菊井住職
称名寺は門徒さんの声も住職の声も両方大切にされているところが良いところだと思いますね。どちらかに偏るとしんどくなるので、お互いの声を、こんな風にお茶やお酒を飲みながら、お弁当いただきながらあれやこれや話し合える、聞き合える関係が出来ている事がとても大事だと思います。
2022年7月25日
本のご紹介(東本願寺)
著者 東舘紹見氏(大谷大学教授)
発行 東本願寺出版
発刊 2022/7/5
頁数 180頁
価格 4,400円(税込)
2022年度開催の安居次講(7/17~7/31)の内容が記載されております。
2023年2月に三条教務所で『秋安居』が開催されます。本書の内容を中心に講義されますので是非お買い求めください。
購入をご希望の方は三条教務所までご連絡ください。(0256-33-2805)