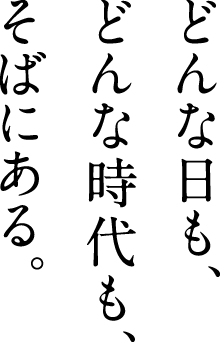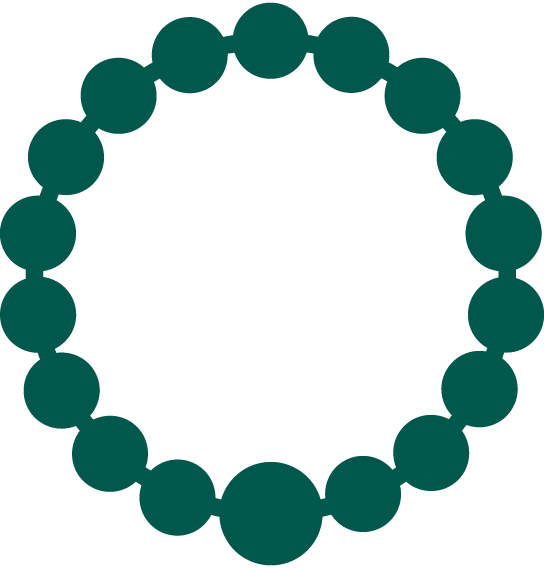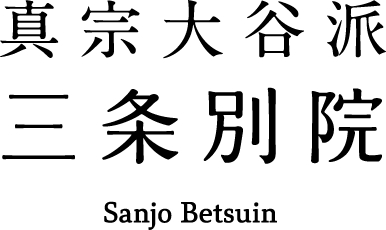2020年10月23日
DODALO「あなたはどんな自分になりたいですか?」
「愚者になりて往生す」
『末燈鈔』(親鸞聖人のお手紙)/『真宗聖典』603頁
【解説】
浄土真宗は「愚」という言葉をとても大切にしています。
親鸞聖人は自らを「愚禿釈親鸞」と名のられました。また、その聖人の師である法然上人は、比叡山で「智慧第一の法然坊」と称されながらも、自らを「愚痴の法然坊」と表明しています。ともに自分が「愚」であることを公に語っているのです。なぜそのようなことを公言しているのでしょうか。
一般的に、このような宣言は、謙遜の言葉として受け取られているようですが、私たちの日常の感覚からすれば、あえて自ら誰かにマイナスと受け取られかねない自分を打ち明けることはまず有り得ません。もし、それがあるとするならば、正直に話すことで好感を持たれるのでないか、失敗を大目に見てもらえるのでないか等と、自分の利になる目算がある場合でしょう。私たちが普段使っている謙遜はそのような範疇に納まるものだと思いますが、親鸞聖人たちの名のりもそれと同じような計算高いものなのでしょうか。
また一方で、この「愚」の名のりが、計算ではなく、偽りない自らの事実を語るものとするならば、それは、ただいたずらに自分を卑下するものではないのかと感じる方もいるかもしれません。そこで、親鸞聖人が「愚」という言葉をどのようにいただいていたのかをうかがい知ることのできるエピソードに目を通してみたいと思います。親鸞聖人が晩年に書かれたお手紙の一節で、若かりし頃出会った師、法然上人についての回想です。
故法然聖人は、「浄土宗のひとは愚者になりて往生す」と候いしことを、たしかにうけたまわり候いしうえに、ものもおぼえぬあさましき人々のまいりたるを御覧じては、往生必定すべしとてえ〈笑〉ませたまいしをみまいらせ候いき。ふみざた〈文沙汰〉して、さかさかしきひとのまいりたるをば、往生はいかがあらんずらんと、たしかにうけたまわりき。いまにいたるまでおもいあわせられ候うなり。(『真宗聖典』603頁)
「ものもおぼえぬあさましき人々」とは、身分が低く貧しいために十分な知識を持つこともできず、たのむべき力を持たない人々です。誇るべきものをなにも持たない者こそ、自らを取り繕うようなことをせず、むしろまっすぐに浄土の教えに耳を傾けることが出来るのだと思います。等身大の自分をもって、道を求めて尋ねて来られる人々をご覧になって、「あの方々の往生は間違いないであろう」と法然上人は微笑んでおられたということです。
「ふみざた(文沙汰)して、さかさかしき(賢々しき)ひと」とは、自分の学び得たことを振りかざして論評し、自分を誇ろうとしていかにも賢そうに振る舞う人のことです。おそらく、この人たちはふざけているわけでも、怠けているわけでもなく、むしろ、真面目で一所懸命努力していたと思います。にもかかわらず、法然上人は「往生はどうであろうか」といぶかしげにおっしゃっています。どこに向かって、その一所懸命な努力がなされているのかを問いかけているのです。
私たちの日常でも、少しでも優れた自分、価値のある自分としてアピールして他者に認めてもらおうとすることがままありますが、それは何のためなのか、よく考えてみると、優れた自分、価値のある自分、役に立つ自分、そのような善き自分の方が、人や社会に受け入れられていくのであろうと心のどこかで感じているからではないでしょうか。それは裏を返せば、善き自分でなければ、相手にされなかったり、見限られたり、居場所を失ったりするのではないか、「善きものでなければ見捨てられるのではないか」という恐れを抱えているということです。時代・社会からの問いかけも厳しいですし、学校や会社、友人関係など、様々な場で、評価や選別にさらされてきた私たちは、それを無言の圧力として肌で感じてしまうのだと思います。
これは一見すると他者や世間の声なき声に対する怯えのようですが、その根底に劣った、価値のない、役に立たないような悪しき自分であれば、それは自分として受け取ることが出来ない、認めたくないという自己不信があるわけです。他ならぬ自分自身が自分を追い詰めているならば、それはあまりに悲しいすがたではないでしょうか。
理想や目標を掲げてそれに向かって一所懸命に努力することは、人として生きていく上でとても大切なことですが、その過程で知らず知らずのうちに、理想に叶わない現実の自分自身や他者を蔑み、ないがしろにして、傷つけることになっているとしたら、それは私たちが本当に望んでいることではないはずです。他者が私のことを必要としてくれるか、認めてくれるかどうかは、相手に任せなければならない事柄ですが、自分のことをどうするのかは、私たち一人ひとりの意志に委ねられています。たとえ、この自分がどれほど小さくつまらないものとして、今見えようとも、その自分こそがすべての道を開いていく鍵となるのでしょう。どんな自分であっても「これが私です」と受け取っていけるところに本当に自由な生き方があるのではないでしょうか。
そして、このお手紙で大事なことは、晩年の親鸞聖人が「いまにいたるまで」ありありとこのお話を思い浮かべているということです。もし、親鸞聖人が当たり前のように、自らの愚かさを自覚して、等身大の事実の自分自身に立って生活しているならば、少なくとも晩年になるまでこの法然上人のお話を思い浮かべ続けることはなかったと思います。むしろ、いつでも賢そうに分かっている者として、自身を問うことも教えられることもなく、自分や他者を踏みつけて顧みないような自分がいたからこそ、この法然上人のお話が親鸞聖人の生涯にわたって突き刺さり続けたのでしょう。分かっている者ではなく、教えられなければならない者として、法然上人の言葉やすがたを通して、仏の教えに自分自身を照らされながら歩まれたのが、親鸞聖人の「愚」の名のりの具体的な中身であると思います。聖人は、知らず知らずの内に、自らの前提としてしまっている生き方の危うさを、そのような形で確かめながら、まわりの人たちにも伝えていました。自分自身の生き方とは、当たり前の前提としてもつものではなく、教えられ、学び続けねばならないものであることを、私たちに示してくださっているのです。
富樫大樹
妙音寺(新潟市西区)