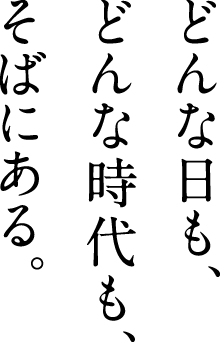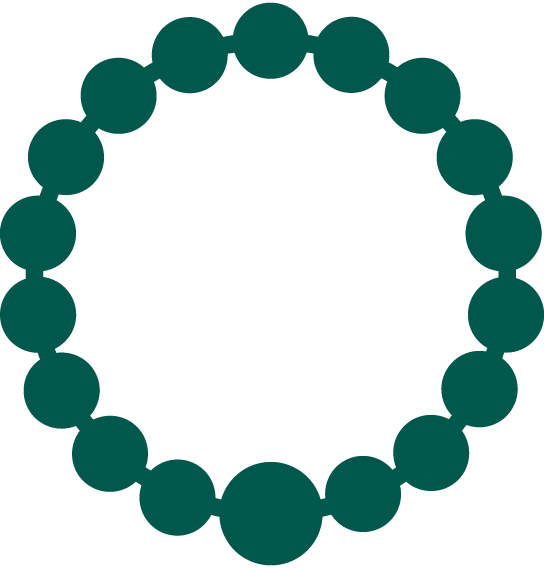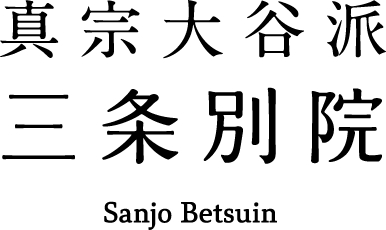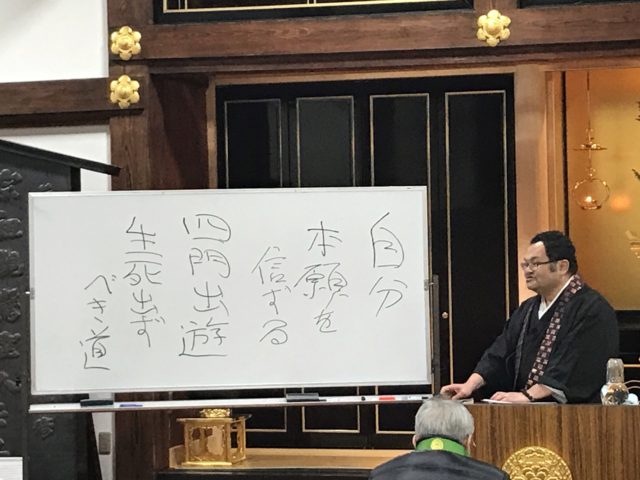2019年1月27日
廣河が「『歎異抄』に聞く」を聞く。-第十五章-
もうそろそろ2月になってしまいますが…あけましておめでとうございます。廣河が「『歎異抄』に聞く」を聞く。新年を迎えようやく平常運転、第八回目です。旧年中はご愛顧いただき誠にありがとうございました。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
年末年始、皆さんはどのように過ごされましたか?廣河は除夜の鐘、修正会に加え、冬期休暇中も休暇を返上して別院の留守を預かっておりましたので、これまで自坊で過ごしてきた年末年始とは全く違う日々を過ごさせていただきました。何故休暇返上?と思われるかもしれませんが、実は廣河、2月末にお釈迦様生誕の地、インドに旅行の予定がありまして…。その旅行のために休みを返上したのですね。また詳しく書くかもしれません。さて、
12月28日(金)に宗祖御命日日中法要が勤められました。その後の御命日のつどいでは、『歎異抄』をテーマに、第一章から順にご法話を頂いています。今回は三条教区15組長泉寺(三条市上保内)の石塚祐堂氏に、『歎異抄』「第十五章」を主題にご法話頂きました。
『歎異抄』「第十五章」
一 煩悩具足の身をもって、すでにさとりをひらくということ。この条、もってのほかのことにそうろう。
即身成仏は真言秘教の本意、三密行業の証果なり。六根清浄はまた法華一乗の所説、四安楽の行の感徳なり。これみな難行上根のつとめ、観念成就のさとりなり。来生の開覚は他力浄土の宗旨、信心決定の道なるがゆえなり。これまた易行下根のつとめ、不簡善悪の法なり。
おおよそ、今生においては、煩悩悪障を断ぜんこと、きわめてありがたきあいだ、真言・法華を行ずる浄侶、なおもて順次生のさとりをいのる。いかにいわんや、戒行恵解ともになしといえども、弥陀の願船に乗じて、生死の苦海をわたり、報土のきしにつきぬるものならば、煩悩の黒雲はやくはれ、法性の覚月すみやかにあらわれて、尽十方の無碍の光明に一味にして、一切の衆生を利益せんときにこそ、さとりにてはそうらえ。
この身をもってさとりをひらくとそうろうなる人は、釈尊のごとく種々の応化の身をも現じ、三十二相・八十随形好をも具足して、説法利益そうろうにや。これをこそ、今生にさとりをひらく本とはもうしそうらえ。
『和讃』にいわく「金剛堅固の信心の さだまるときをまちえてぞ 弥陀の心光摂護して ながく生死をへだてける」(善導讃)とはそうらえば、信心のさだまるときに、ひとたび摂取してすてたまわざれば、六道に輪廻すべからず。しかればながく生死をばへだておうろうぞかし。かくのごとくしるを、さとるとは言いまぎらかすべきや。あわれにそうろうをや。
「浄土真宗には、今生に本願を信じて、かの土にしてさとりをばひらくとならいそうろうぞ」とこそ、故聖人のおおせにはそうらいしか。(『歎異抄』真宗大谷派宗務所出版部)
【試訳】
「信心を得たならば、あらゆる煩悩を備えた身のままで、さとりを開くことができる」と主張することについて。この主張は、もってのほかのことである。
即身成仏(この身のままで仏に成ること)という教えは真言密教の根本義であり、三密行業の証果である。六根清浄という教えは、法華一乗の説くところであり、四安楽の行によって得られる功徳である。これらはみな、特に秀でた能力によって行ずることのできる難しい修行であり、精神統一して仏、菩薩をイメージすることにより成就するさとりである。それに対して、人間の時間意識を破って未来から開かれてくるさとりは、絶対他力を根本義とした浄土真宗の教えである。すなわち、いま、ここで本願力の信心に身も心も定まる道である。これこそ、まったく人間の能力や努力を必要としない普遍的な行であり、善人や悪人という相対的な意味づけや人間の小さな努力を救いの条件とはしない教えである。
だいたい、いのちのある間は、欲望や怒り、罪の意識を断ち切ることは、まったく困難であるから、真言や法華の行者ですら、次の生でさとりを開くことを祈るのである。まして、われらのように戒律や修行や知恵のないものが、この世で「さとり」を開くことなどないのである。しかし、阿弥陀の本願の船に乗って、迷いや罪で満ち満ちた苦海を渡り、浄土の岸に到着したならば、黒雲のような欲望や怒りの感情が晴れ、たちまちに真実が月明かりのように輝き、あらゆるところを照らす阿弥陀の光とひとつになって、あらゆる人びとを救うときにこそ、「さとり」とは表現するのである。
この身をもったままでさとりをひらくと言うひとは、お釈迦様のように、さまざまな姿をとって現れ、三十二相・八十随形好という瑞相を具え、法を説き、人びとを救いとろうとでもいうのだろうか。こういう基準を満たしてこそ、この世で「さとり」を開くと言いうるのであろう。
親鸞聖人の『和讃』には、「金剛堅固の信心の さだまるときをまちえてぞ 弥陀の心光摂護して ながく生死をへだてける」(決して壊れることのない信心が定まる、そのとき、阿弥陀如来の光に摂め取られ、永遠に迷いのいのちを超えたのである〈善導大師を讃嘆した和讃〉)とある。これは、信心が決定したとき、二度と捨てることのない阿弥陀の救いに摂め取られるならば、六道という迷いの生を繰り返すことはない。そうすれば、永遠に迷いの生活を超越することができるのである。このように受け止めることを、「さとる」というのである。混乱してはならない。まったく哀れなことである。
「浄土真宗の教えは、いま、阿弥陀の本願の教えを信じ、彼の土でさとりを開く」と、いまは亡き、親鸞聖人は仰せられたのである。
【語註】
三密行業の証果…身に印契を結び、口に真言を唱え、意(心)に仏を観ずるという密教の実践法。証果はさとりのこと。
六根清浄…眼・耳・鼻・舌・身・意という六根を整えて、自由自在な智慧のはたらきを得ること。人間の身心が清らかになった状態。
法華一乗の所説…すべての者が等しく救われると説く『法華経』の教え。
四安楽(しあんらく)の行…身口意のあやまちを離れる三善行と、慈悲行との、心身を安楽にする四つの行法。六根清浄はこの行によって感得される。自己の身心と他のひとを安らかにするための修行。
不簡善悪(ふけんぜんあく)の法…人を善悪で区別しない、平等に救済される道。
戒行恵解(かいぎょうえげ)…戒を保って修行し、智慧をもって道理を正しく理解すること。
法性の覚月…涅槃のさとり。これを闇夜を払う月に譬える。
応化の身…衆生を救うために、相手の願いに応じて、衆生の姿をとって現れた仏身。
三十二相・八十随形好(ずいぎょうこう)…仏の身体にそなわる、さまざまなすぐれた特徴。
第十五章は念仏者における「即身成仏の主張」を批判し、浄土真宗のさとりを明らかにするということに、焦点があります。さとりを開くことができるのは「この世」か「あの世」か。ここで聖道門の代表として挙げられている真言宗、法華宗は、この世でさとりを開くことを主眼としますが、浄土教では「彼の土のさとり」を説きます。
冒頭の異議者の主張は「煩悩をそなえた身のままで、さとりを開くことができる」というものです。こういった異議がなぜでてくるのか。これは、『親鸞聖人御消息集』すなわち親鸞聖人のお手紙の中で、親鸞聖人自身が「真実信心をえたる人をば、如来とひとし」と語っていたことに起因します。
まことの信心をえたる人は、すでに仏にならせ給うべき御みとなりておわしますゆえに、如来とひとしき人と経にとかれ候うなり。弥勒はいまだ、仏になりたまわねども、このたびかならずかならず仏になりたまうべきによりて、みろくをばすでに弥勒仏と申し候うなり。その定に、真実信心をえたる人をば、如来とひとしとおおせられて候うなり。また、承信房の弥勒とひとしと候うも、ひが事には候わねども、他力によりて信をえてよろこぶこころは如来とひとしと候うを、自力なりと候うらんは、いますこし承信房の御こころのそこのゆきつかぬようにきこえ候うこそ、よくよく御あん候うべくや候うらん。自力のこころにて、わがみは如来とひとしと候うらんは、まことにあしう候うべし。他力の信心のゆえに、浄信房のよろこばせ給い候うらんは、なにかは自力にて候うべき。よくよく御はからい候うべし(『真宗聖典』『親鸞聖人御消息集(広本)』五七九頁)
正嘉元(1257)年、親鸞聖人85歳のときに、弟子の浄信に宛てた手紙です。その内容は、承信が「如来とひとしというのは自力の信である」と批判していると浄信が伝えたことについて親鸞が返信して、「いま少し深く承信房には考えて欲しい」と承信の指摘を否定している内容です。
信心よろこぶ人を如来とひとしと同行達ののたまうは自力なり。真言にかたよりたり(『真宗聖典』『御消息集(善性本)』五八三頁)
これが承信の批判内容ですね。つまり、「信心をよろこぶ人を如来と等しいと貴方たちが言うのは、それは自力だ。真言宗(の即身成仏の説)に偏っている」といった内容です。
親鸞聖人は真宗の信仰を「如来とひとし」と積極的に表現したのですが、それがかえって門弟たちに誤解を与えてしまい、それで今回のような異議が出てきた、というわけですね。ちなみに親鸞聖人は「如来とひとし」について、以下のように述べています。
浄土の真実信心の人は、この身こそあさましき不浄造悪の身なれども、心はすでに如来とひとしければ、如来と申すこともあるべし(『真宗聖典』『御消息集(善性本)』五九一頁)
つまり、身体とこころは別の次元にあることをいい、こころが如来と同じなのだと説明しています。しかし、真言宗の「即身成仏」は心身ともに仏と一体になろうとすることであるため、微妙ですが違います。このあたりが曖昧であったり取り違えてしまうと、今回の異議者の主張のようになっていくわけです。
さて、ご法話ではまず、この第十五章が誰に対して書かれているのか、ということを問いました。すなわち、それは自分。「他の誰か」ではなく、「自分自身」に書かれていると。何故そういえるのか。親鸞聖人の言葉は、至ってシンプルです。「浄土真宗には、今生に本願を信じて、かの土にしてさとりをばひらくとならいそうろうぞ」。本願を信じなさい、他に何もないよと。しかし、この言葉を聞いて、迷っているのは誰だろうか。他ならぬ私自身なのではないかと。むしろ、頭では「煩悩具足の身をもって、すでにさとりをひらく」と考えているのではないか。そこに、信じきれない自分が生まれてくる。だからこの第十五章は、「自分自身」のために書かれていると言われました。
さらにご法話では、「さとりを開く」とはどういうことなのかということを言われ、四門出遊のお話をされました。元々国の王子であったお釈迦様が、国の東西南北にある四つの門においてそれぞれ、老人に出あい、病に苦しむ人に出あい、死に至る人に出あい、最後に出家者の姿に出あい、修行され、菩提樹のほとりにてさとりを開かれた。この老病死、そしてこの身が生まれてきたということを含め生老病死、それらの出あいを通して、一番何を願われたか…。
併せて、親鸞聖人の妻である恵信尼がその娘の覚信尼に出していたお手紙の中の言葉を紹介されました。それは、「生死出づべき道」。生死(しょうじ)というのは、生と死と書いて生死と言うけれども、それは生まれきた苦しみ悩み、生きていく苦しみ悩み、そして死に至らんとする苦しみ悩み。それは迷いの姿であると。その、迷い、苦しみを、どうやったら超えていけるのか。そこを一番求めていくのが、仏道なのであったと、石塚さんは言います。お釈迦様も、親鸞聖人も、法然上人もみな、「生死出づべき道」を求めていたのだと。
そして、求めていく中で何に気が付くか。どうしたら超えていけるのかといった時に、生死ということが、迷いではあるんだけれども、同時に「身の事実」と読めるんじゃないかと。我らは生まれて生きて、いずれ死ぬ。この「身の事実」ということを自覚させていただくのが、仏道なんじゃないか。それは、「どうにかなる我が身」を教えているわけではない。むしろ「どうにもならない我が身」にぶち当たっていく。この身はさとりを開ける身ではない。煩悩具足の凡夫なんだ。けれども、自分の能力とは全く関係なく、阿弥陀の本願を信じさせていただいて、浄土に往生させていただき、仏と成らせていただく。その歩みが仏道であり、浄土真宗なのだと言えます。
大事なことは、教えを教えとして、「私」は素直に聞けているのかということ。そして、廣河は素直に石塚さんのお話を聞けているのかということ…。あなたは、目の前のその人の話を、素直に聞けていますか?
明日、1月28日(月)の御命日のつどいでは、『歎異抄』第十六章をテーマに第17組稱名寺の有坂次郎さんよりお話しいただきます!